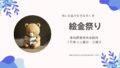牛のような胴体、長い首、天を衝くように突き出した角を持つ鬼の顔。巨大な山車が、真夏の宇和島の街を悠然と進んでいきます。人を襲う恐ろしい妖怪なのか、悪霊や邪気を祓う神なのか。畏怖と信仰の対象である牛鬼の姿は圧巻です。
牛鬼
頭が牛で胴体が鬼、頭が鬼で胴体が牛。
地域によって姿形は異なりますが、牛鬼の伝説の多くは、毒を吐いたり人を食い殺したりする獰猛で残忍な妖怪と言われています。


牛鬼って、これじゃないの?

それは土蜘蛛だよ。
牛鬼も土蜘蛛も、それぞれ違う妖怪なんだけど、伝承が広がる間に混同されるようになったんだ。
牛鬼と土蜘蛛の共通点
- 人里離れた山中や洞窟に住んでいる。
- 毒を吐いて人に襲いかかってくる。
- 非常に強力な力を持ち、恐ろしい異型の姿形をしている。

山奥で恐ろしいものに出会った。
毒を吐いて、襲いかかってきた。
顔は鬼、身体は牛で、大きな化け物だった。

山奥で恐ろしいものに出会った。
毒を吐いて、襲いかかってきた。
顔は鬼、身体は牛みたいに大きな化け物だった。

山奥で恐ろしいものに出会った。
毒を吐いて、襲いかかってきた。
顔は鬼、身体は牛みたいに大きな蜘蛛の化け物だった。

牛鬼?
牛に見えないよ

江戸時代、それまで口承や文献で語られていた妖怪たちの姿を初めて絵にした画家鳥山石燕(とりやま せきえん)が、『画図百鬼夜行』に描いた牛鬼が牛の頭に毒蜘蛛のような胴体だったことも、牛鬼と土蜘蛛が混同される原因かも。
愛媛県の牛鬼伝説
愛媛県宇和島地方(喜多郡河辺村、現在の大洲市)の牛鬼伝説
昔々、喜多郡河辺村に牛鬼が現れ、人や家畜を襲われました。
牛鬼を退治するため、村に山伏がやってきました。
山伏がホラ貝を吹き真言を唱えると、屈強な牛鬼も怖気立ちました。その機に乗じて、山伏は牛鬼の眉間を剣で貫き、体をバラバラに斬り裂いたと伝えられています。
斬り裂かれた牛鬼の体からは7日7晩、血が流れ続け、大きな血溜まりとなりました。
その場所は現在、牛鬼淵と呼ばれています。
鬼が城の牛鬼伝説
宇和島市と北宇和郡津島町との境に、鬼が城という山があります。
昔々、鬼が城には牛鬼が住んでいて、夜な夜な村人を食べていたそうです。
その牛鬼をおとぎ話で有名な桃太郎が退治した、という伝承が残っています。
うわじま牛鬼まつり
愛媛県宇和島市は、伊達政宗の長男伊達秀宗(だて ひでむね)が初代宇和島藩主となって以来、城下町として栄えました。

お父さんの伊達政宗(だて まさむね)は、奥州(現在の東北地方)を拠点に勢力を拡大し独眼竜の異名で恐れられたんだよ。豊臣秀吉や徳川家康とも競い合い、仙台藩の初代藩主として東北の礎を築いた人物なんだ。

伊達秀宗は伊達政宗の長男なんだけど、側室の子供だったから、仙台藩の次期藩主は正室の子供の次男が継ぐことになったんだ。
和霊神社
牛鬼まつりの始まりは、宇和島市にある和霊神社(われいじんじゃ)の祭事に関係しています。
伊達秀宗に仕えた家老山家清兵衛(やんべ せいべえ)が1620年に政敵によって暗殺されました。
その後、この事件に関わった人物が次々と不審な死をとげ、人々は山家清兵衛の怨霊によるものだと恐れました。
これを鎮めるために建立されたのが和霊神社です。
1653年、山家清兵衛の死後33年忌にあたる年に、藩主伊達秀宗が和霊神社を建立し、盛大な祭典を行ったのが和霊大祭(われいたいさい)の始まりとされています。
牛鬼の練り物

練り物は、祭礼の行列に登場する、様々な趣向を凝らした神輿や山車のことだよ。
江戸時代中期(1700年代半ば以降)、南予地域(現在の愛媛県の南西部)に、恐ろしい牛鬼の姿を模した練り物がの神社の祭礼に登場するようなります。
災厄をもたらす存在が逆に魔除けとなる存在として、祭りの先頭を務めることになりました。

牛鬼まつりは、和霊大祭と、地域に伝わる牛鬼を厄除けとして練り歩かせる練り物文化が結びつき、さらに近代になって市民参加型の祭りへと発展していきました。
2025年 牛鬼まつり

開催日時
2025年7月22日(火曜日)、23日(水曜日)、24日(木曜日)
7月23日 和霊大祭 例祭
7月24日 子ども牛鬼パレード 親牛鬼パレード
開催場所
愛媛県宇和島市
アクセス
車の場合
宇和島道路「宇和島朝日IC」から約2km、約5分
電車の場合
JR宇和島駅から徒歩約7分